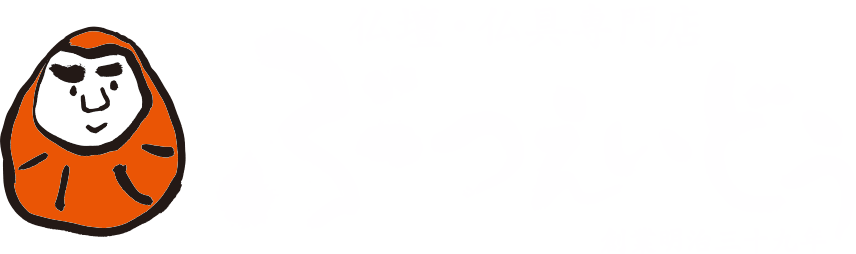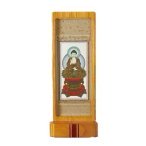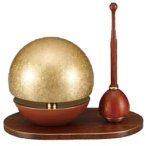- 数珠の選び方にルールってあるの?
- 宗派によって形が違うって聞いたけどホント?
このような疑問にお答えします。
数珠といっても、いろんな素材や形・色があり、お値段も安いものから高いものまで本当にたくさんあります。いざ買おうと思っても迷ってしまう、どれを選んだらいいのかわからない・・・という方も多いのではないでしょうか?
実は数珠は使い方によって選ぶべき形や色が異なります。ここを考えずに購入してしまうと失敗してしまうことも・・・。
そこでこの記事では、創業明治39年の仏壇・仏具専門店が数珠の用途によってどんな数珠を選べばよいか詳しく解説させていただきます。
- 数珠の種類がわかる
- あなたに最適な数珠の選び方がわかる
数珠選びの基本知識: より良い選択をするために

そもそも数珠って何?
お葬式などの法事に欠かせない数珠。片手に掛けている人もあれば、両手を数珠の内側に入れて拝む人もあれば、両手でもみながら一心に念仏を唱える人もあります。
つまり仏前で拝むときに手にかけて使うもの、というのが一般的な認識かと思います。まさにその通りです。仏前で拝むときは誰もが持っていなければならない法具が数珠です。
実は、本来の数珠の使い道は「自分が唱えた念仏や題目の回数を数える」というものです。念仏を一回唱えたら、主玉を一つたぐるというように数えます。なので厳密には、単に手に掛けていればよいものではなく、両手で揉むようなことも数珠を傷めてしまいますので好ましくありません。
とはいえ、本来の使い道を知ると「数珠」という名前にも納得しますよね。数珠には珠数、念珠など他の表記がありますが、同じものを指します。それぞれ、「数える(ための)珠」「珠で数える」「念じる(のに使う)珠」といったところでしょうか。(この記事では、数珠という表記で統一します。)
数珠の選び方にルールはあるの?
数珠選びは、宗派や用途、男女別、素材やデザインなど様々なポイントを考慮しながら、自分に合った念珠を見つける大切なプロセスです。まずは、数珠の種類や選び方の基本知識を身につけることが、より良い選択をするために重要です。
選び方のポイントとして、以下のようなものが挙げられます。
- 宗派による違い
- 男性用と女性用の違い
- 素材や色の好み
- 用途や価格帯
これらの基本知識を踏まえて、数珠選びを楽しみ、最適な一本を見つけましょう。
男性用と女性用の違い: 玉の大きさやデザインに注目
男性用と女性用の数珠は、主に玉の大きさやデザインに違いがあります。男性用は大きめの玉を用いた力強いデザインが多く、女性用は小さめの玉を使った繊細なデザインが特徴です。また、女性用の数珠には色石や水晶を使用したものが多いため、色のバリエーションも豊富です。自分の好みや手のサイズに合ったものを選ぶことが大切です。
略式(片手念珠)と本式(宗派別念珠)の選び方: 目的に応じて選択
略式(片手念珠)と本式(宗派別念珠)は、それぞれ用途や目的に応じて使い分けられる数珠の種類です。
略式は一般的なお参りや家庭内での使用に向いており、本式は法事や葬儀などの場に使用されることが多いです。
また、宗派別念珠はそれぞれの宗派ごとに規定された形や素材が決まっているため、自分が所属している宗派の数珠を選びましょう。
あらかじめこれを知っていただくことで、数珠選びが少し楽になりますよ。
宗派別の数珠選び方: 浄土宗、真言宗、日蓮宗などそれぞれの特徴を理解
数珠選びの際には、宗派ごとの特徴を理解することが重要です。それぞれの宗派には異なる玉数、房の色、素材などがありますので、自分が所属する宗派に応じた数珠を選ぶ必要があります。ここでは、浄土宗、真言宗、日蓮宗をはじめ、各宗派の基本的な数珠選びのポイントについて詳しく解説していきます。
まず、浄土宗では、男性用の数珠には108珠、女性用には36珠が一般的です。また、房の色は紫色が用いられることが多く、水晶、黒檀、菩提樹などの素材が好まれます。
真言宗では、男女ともに108珠を使用し、房の色には宗派によって違いがありますが、一般的には黄色が使われます。素材には天然石や木材が用いられることが一般的で、その中でも水晶や翡翠がよく利用されます。
日蓮宗では、男性用には108珠、女性用には54珠が選ばれることが多く、房の色は青色が好まれます。素材は梵天やオニキス、翡翠が一般的です。
他の宗派においても、それぞれ独自の特徴がありますので、自分の宗派や好みに合った数珠選びが大切です。さらに、お念珠や葬儀の際に用いられるもの、法事用のものなど、用途ごとに適した数珠を選ぶ必要があります。
宗派別の数珠選びについて理解し、自分に適した素材や玉数、房の色を考慮して選びましょう。質問や確認が必要であれば、適切なアドバイスを提供してくれる仏具店や専門家に相談することもおすすめです。
素材や色にこだわった数珠選び: 木材、天然石、パワーストーンなど
素材や色にこだわった数珠選びは、自分と相性の良いものを見つけるために重要です。木材、天然石、パワーストーンなど、様々な素材が利用されています。
色も重要なポイントで、好みや宗派によって異なります。男性は黒、女性は白が一般的ですが、最近では個性を重視したカラフルな数珠も増えています。
数珠に使われる素材とは?
まず木材は、黒檀や菩提樹など種類が豊富で、それぞれに異なる質感や風合いがあります。また、木材は使用感が出るほどに味わいが増す点も魅力です。
一方、天然石は水晶や翡翠、オニキスなどが人気で、石によってもたらされるとされるパワーやお守り効果を重視する方に適しています。
パワーストーンは、エネルギーを持つとされる石が用いられており、様々な効果が期待できるので自分に合ったものを選ぶことが大切です。
房の形の違いや房の素材は?
房の形はいくつか種類がありますが、大きく分けると4種類になります。
切房、頭付房、梵天房、紐房です。どの房を選ぶかは決まりはありませんが、本式数珠ですと房の形が決まっているものもあります。略式数珠であればお好みの形をお選びいただくと良いでしょう。
また、数珠を探していると「正絹」「人絹」といった表記を目にするかと思います。これは房の素材を表しています。「正絹」は天然の絹(シルク)を指します。本絹と表記することもあります。
これに対して「人絹」は、人工的な絹ということで化学繊維(アクリルやポリエステルなど)を指します。
比較してみると、正絹の方がやはり繊維がしなやかで、さらさらとした手触りです。人絹はそれに比べるとやや硬さがあります。実店舗などで直接触れることができる場合は、ぜひ手に取って比べてみてください
数珠の価格帯別選び方: 予算や用途に合った数珠を見つけるポイント
数珠の価格帯別選び方は、予算や用途に合ったものを見つけるために重要です。まず、価格帯に影響する要素として、素材や職人技、サイズがあります。素材の価値や希少性、手間がかかる加工方法が使用されるほど、価格が上がります。
また、用途に合わせた選び方がポイントです。例えば、法事や葬儀に使う場合は、宗派やマナーによって選ぶべき数珠が決まっています。このような場で重要なのは、適切な数珠を選ぶことで、故人への敬意を示すことです。
一方、日常的なお守りとして使用する場合は、デザインやパワーストーン効果など、自分の好みや目的に合ったものを選ぶことが大切です。この場合は、散財を避けるためにも予算内で選ぶことが重要です。
また、初めて数珠を購入する方や、予算が限られている場合は、お手頃価格のものから始めることをおすすめします。価格帯によって劣る品質ではなく、コストパフォーマンスが良いものも多く存在しています。
高級数珠の選び方: 上質な素材や職人技によるクオリティー
高級数珠の選び方には、上質な素材や職人技によるクオリティーが重要です。素材は、希少性の高い天然石や高級木材が用いられており、見た目や手触りにも独特の高級感があります。
また、職人技によって細やかな彫りや繊細な紐縄で結ばれた数珠は、一目置かれること間違いなしです。特に、日本の職人による手作り品は世界的にも評価が高く、信頼性があります。
さらに、高級数珠はその持つエネルギーやパワーも強力とされており、多くの人から愛用されています。ただし、高級数珠は他の価格帯のものに比べてお手入れやメンテナンスに注意が必要です。
お手頃価格の数珠探し: コストパフォーマンスを重視した選択
お手頃価格の数珠探しでは、コストパフォーマンスを重視した選択が大切です。まず、価格が手頃であっても品質やデザインに妥協しないものを選ぶことが肝心です。
また、自分の用途や好みに合ったものを見つけるため、数珠専門店や仏具店で相談や試着をすることをおすすめします。これにより、自分にピッタリな数珠が見つかるでしょう。
さらに、お手頃価格の数珠でも、宗派やマナーに合ったものを選ぶことが重要です。知識を身につけ、正しい選び方をすることが大切です。
最後に、価格だけでなく、アフターサービスや修理対応も考慮することが重要です。万が一の時にも安心できるお店を選ぶことで、長く大切に使える数珠と出会えるでしょう。
数珠の選び方を用途別に6つ紹介!
どんなシーンで使うのか?とりあえず用事に間に合わせるための1本なのか、一生使えるようなきちんとした1本なのか?などを考えることで、目的に応じた数珠の形が見えてきます。
店舗でお客様が数珠をお選びになる時にも、「どういった方が」「どのような目的で」使うのか気を付けて接客するよう心がけています。ここでは、まずは用途別に考えてみたいと思います。
その1:葬儀や法事に持っていく数珠

不幸はないに越したことはないですが、年齢が上がるにつれ、お葬式や法事に招かれることも増えていくかと思います。
「最近、そういう機会が多いな……」そのような場合におすすめなのは略式数珠です。本式数珠でももちろん構わないのですが、自分の宗派の本式数珠を持って他の宗派のお宅を訪問するのはためらわれる、という方はとても多いです。
また、女性の場合は、宗派を問わずお使いいただける二連数珠(振分)も選択肢に入ってきます。
より本式に近いかたち持っていただけますので、たとえば本水晶の白房でしたらどこに持って行っても恥ずかしくない万能選手と言えるでしょう。
最近は白房の中でも、銀糸がワンポイントにあしらわれているものはより高級感があり、見た目にも美しく人気があります。
その2:自宅や、身内の法要で使う数珠

ご自宅に仏壇があるなどして自宅で法要をとりおこなう機会が多い人や、そのご家族は宗派に合わせた本式数珠を持つのがおすすめです。
自分用の法事セットとして、数珠袋に入れた数珠と経本を用意しておくことで、慌てず法要にのぞむことができるでしょう。
三回忌、七回忌などの年忌法要だけでなく、毎年の棚経にお使いいただくことができます。
その3:お墓参りに持っていく数珠

お墓参りに持っていくことを考えるならば、本式か略式かは問いませんが、気軽に使えるような数珠が良いでしょう。
お墓の手入れなどをしているうちに置き忘れてしまって、気が付いて見に行ったら無くなっていた……というのは残念ながらあります。自分で選び抜いた数珠を急に失ってしまったら……悲しいですよね。
こんなお墓のエピソードに、え!?と思われる人も多いかもしれません。でも、筆者の身内で実際にあったことなのです(しかも複数回)。
まあこんな話は珍しいと思われても、フォーマルな場面で使うしっかりした1本とは別に、気軽に外に持ち出せる1本があると何かと便利ですよ。先ほどのように紛失してしまった場合や、知らない間に糸が切れてしまって使えなくなってしまった場合はどちらかが予備として機能します。
地方だと、うっかり忘れないように車に1本忍ばせておくこともありますね。あるいは、まだ数珠を持っていない子どもに、とりあえずの数珠として貸すということもあると思います。
人によっては抵抗があるかもしれませんが、サブとしての数珠、おすすめです。
その4:お遍路に持っていく数珠

お遍路の持ち物として持っていく数珠は、手持ちの数珠がある場合はそれで構いません。
もし、新しく求める場合にも制約はありませんが、真言宗の本式数珠がより適しているでしょう(お遍路の場合、他宗派でも真言宗の数珠を使って大丈夫です)。
というのも、お遍路のお参りは真言宗の作法が基本とされているからです。お遍路は弘法大師ゆかりの地を巡るもので、弘法大師は真言宗の開祖となります。
その5:贈り物としての数珠

数珠を送るタイミングというのはいくつかありますが、多くは成人祝い、就職祝い、結婚祝いなど、いずれも人生の門出のタイミングになります。
成人祝いや就職祝いでは、場面を選ばず使える万能な1本(つまり略式数珠ですね)を贈ります。
あくまで傾向としてですが、男性の場合は青虎目石やソーダライトといった青系や、オニキスやジェット、黒縞瑪瑙など黒系が人気です。女性の場合は本水晶や紅水晶に根強い人気のあるほか、ワンポイントで紫水晶やインド翡翠をあしらった品も人気です。
価格帯でいうと1万~2万円の品がよく選ばれていると思います。今の時代であれば、本人に好みの色を聞いてみたり、いっそ直接選んでもらうのも良いでしょう。
結婚祝いの場合は、嫁いでいく娘に、親からのプレゼントとして贈る場合が多いですね。
よく選ばれるのは本水晶に白房を合わせたものや白の淡水真珠に白房など、ホワイトを基調としたものです。二連でも良いですし、相手方の宗派があらかじめわかればその宗派の本式数珠を選んでも良いと思います。
選択肢が多いので価格帯も広いですが、ずっと長く使っていくものになりますので、珠の大きさや形状・房の仕立てを見て両家の前で使うにふさわしい、かつ本人にぴったりな一本を選びましょう。
ちなみに私は淡水真珠の略式数珠を母から受け取り、今も大事に使っています。
その6:子どもに持たせる数珠

年齢によって選ぶのが少し難しいですが、乳児~小学校低学年までは、お子さま用の数珠として販売されているものでおおよそ問題ないでしょう。
多くはプラスチックのビーズでできており、単色のものもあればカラフルなものもあります。
房の形は松房、梵天房、紐房など大人顔負けのバリエーション。
お子さま用の数珠の中でも当店で一番人気なのは「さくらんぼ房」の数珠です。さくらんぼのように並んだ2つの梵天房が愛らしく、5色から選べるので兄弟姉妹で持つことができますよ。
小学校高学年のころになると、お子さま用の数珠では小さくなってきますし、好みもはっきりしてきます。
大人と同じものの中から、予算と本人の好みに合ったものを揃えましょう。
だいたい1万円未満で探す方が多いですね。また、当店では数珠と数珠袋のセットをメンズ用・レディース用ともに用意しています。まずは形だけ揃えたい!という方におすすめのセットです。
こんな視点も!実用性で選ぶ数珠
携帯性で選ぶ
携帯のしやすさというと、重さや大きさがそれに当たります。たとえば、木の珠のほうが石の珠よりも軽い、というのは想像しやすいと思います。
また、男性用として仕立てられた数珠には大きな珠を使用したものもあります。天然石で大きな珠を使用している場合、すごく重厚感があり素敵なのですが、やはり重くなることが多いです(素材にもよりますが)。
ちなみに、使用されている珠が大きいのか小さいのかは、珠の数でだいたい判別することができますよ。「27玉」と書いてあるものよりも、「22玉」「18玉」と珠の数が少ないほうが、珠は大きくなります。
ただ、重そうだからと言って大きな珠の数珠を避けるのではなく、使用する人の手に合わせて、バランスよく選ぶのがコツです。大きく、ごつごつした手の人には大きな珠の数珠がよく合いますし、反対にに華奢(きゃしゃ)でしなやかで小さめの手の人には小ぶりの珠の数珠がよく合うでしょう。
保管のしやすさで選ぶ
房の形状や、珠の素材そのものの特性に注目するとよいでしょう。
房の形には、頭付房(房頭から糸が垂れている)、梵天房、紐房などいくつかの種類があります。頭付房のように糸が垂れているタイプは、使わない間に糸にクセがついてしまい、いざ使おうと取り出したら房が寝ぐせのように乱れていた……ということがあります。
時間があればクセを直すこともできますが、急な用事であったり、私のようにズボラだと難しいですよね。
梵天房であれば房が球体になっていますので、クセがついてしまうことはありません。また、紐房も乱れにくい形だと思います。
珠の素材は、最近の数珠は本当にいろいろな素材を使うようになっているので、気になる素材があれば素材名で検索して調べてみましょう。
衝撃に強いのか弱いのか(キズつきやすさ)、時間で変質することがあるか、熱や水にはどうか……など自分で気になるポイントを調べると、選んだ数珠への思いも深まりますよ。
数珠の使い方とメンテナンス: 大切に長く使い続けるために
数珠は宗派や用途によって形や素材が異なりますが、基本的な使い方は共通しています。まず、お勤めの際には、数珠を両手で持ち、親玉が下になるように手にかけます。そして、念珠を数えながら、お経を唱えます。また、数珠を使う場面では、法事や葬儀などのマナーが重要です。これらの場で数珠を持つ際には、曹洞宗・臨済宗では右手に、それ以外の宗派では左手に持ちます。
メンテナンスにおいては、定期的な手入れが大切です。汗や皮脂が付着したまま放置すると、珠の輝きが失われたり、紐が劣化する恐れがあります。使用後は乾いた布で拭き、湿気のない場所で保管しましょう。また、自分で手入れが難しい場合は、専門の修理業者に相談することも大切です。
正しい持ち方・使い方: 葬儀や法事でのマナーを押さえる
正しい持ち方と使い方を身につけることは、葬儀や法事でのマナーを守る上で重要です。葬儀では、一般的に、片手で数珠を持つのが基本です。真言宗では両手で持つことが一般的で、それぞれの宗派によって若干の違いがありますので、確認しておきましょう。
また、法事では、女性は右手に、男性は左手に数珠を持ちます。数珠を使う際には、親玉を下にして持ち、念珠を指で摘んで数えます。お経の唱え終わりでは、数珠を合掌するようにして持ち、お経を唱えるという流れです。
数珠の手入れ・保管方法: 美しさを保ちながら長持ちさせる
数珠の手入れは、美しさを保ちながら長持ちさせるために重要です。また、手入れ方法によっては、数珠が破損することもあるため注意が必要です。まず、使用後は、柔らかい布で数珠を拭いて汗や皮脂を拭き取ります。また、湿気の多い場所に保管すると珠が変色することがあるため、できるだけ風通しの良い場所に保管しましょう。
数珠に汚れが気になる場合は、専門の業者に相談してから手入れを行うことが望ましいです。また、数珠の紐が劣化してきた場合には、早めに修理や交換を検討しましょう。
数珠選びでよくある質問と回答: 疑問を解決し適切な選択をサポート
数珠選びにおいて、宗派や男性・女性別の適切な房の色や素材など、迷うポイントがたくさんあります。以下では、よくある質問に対して具体的な回答を提供し、適切な選択をサポートします。
– 宗派による数珠の違い: 真言宗では水晶、浄土宗では黒檀など、宗派によって好まれる素材が異なります。また、本式用と略式用にそれぞれ適した数珠があります。
– 男性・女性の違い: 男性用数珠は珠の数が大きく、女性用は小さめです。また、房の色も男性は黒系、女性は白系が一般的です。
– 葬式・法事での使用: 葬式では黒房、法事では紫房が基本ですが、宗派によって異なる場合もあります。事前に確認が大切です。
選び方や宗派別おすすめ品も、専門知識を持った仏具店に相談することをお勧めします。
色や素材の意味と選び方のコツ: 自分に合った数珠を見つける
数珠選びで大切なポイントは、色や素材の意味を理解し、自分に合ったものを見つけることです。以下に、そのコツを説明します。
– 素材の意味: 水晶は煩悩を浄化し、木製は墓参りやお盆に適しています。また、材質や質感も好みや価値観に応じて選びます。
– 色の意味: 黒は厳粛な雰囲気を持ち、白は清らかさを象徴します。また、色の組み合わせによっても意味合いが変わります。
選び方のコツは、自分の好みや価値観に合った色や素材を選ぶことです。専門店でのアドバイスも参考にしましょう。
贈り物や記念品としての数珠選び: 相手に喜ばれるポイントを押さえる
贈り物や記念品として数珠を選ぶ際には、相手に喜ばれるポイントを押さえることが重要です。
– まず、相手の宗派や性別に合った数珠を選びましょう。
– 素材や色は、相手が好むものを選ぶことが大切ですが、実用性も考慮しましょう。
– また、予算に応じて適切な品質のものを選ぶことが重要です。
専門店でアドバイスを受けながら、相手に合った数珠を選びましょう。
まとめ: 数珠選びのポイントを押さえて最適な一本を手に入れよう
数珠選びは、宗派や性別に合わせ、素材や色の意味を理解し、相手が喜ぶポイントを押さえることが大切です。最適な一本を手に入れるために、専門店のアドバイスを活用しましょう。今回の記事を参考に、数珠選びの知識を身につけ、次のアクションに繋げてください。